2018年に廃止された種子法をご存知ですか?
皆さん、Aloha!オガライフライターのMasaeです。
You are what you eat.
あなたはあなたが食べたもので出来ている、という意味のことわざです。
健康な生活を送るために自分やご家族の健康に気を使う方なら、一度ならず耳にしたことがあると思います。
私もその食物の栄養価はもちろん、加工品であれば原材料、野菜なら栽培方法など、自分が口にするものがどのようなものなのかとても気になります。
なぜなら数年前の大病の経験から、自分の体は自分が食べたもので出来ていることを、身を持って知っているからです。
そのため前々回と前回の記事では、以前から気になっていた遺伝子組み換え農作物について書きました。
それを調べていく中で、もうひとつ無視できないと思ったのが『種子法について』です。
少し難しくなるかも知れませんが、お付き合いいただけると嬉しいです。
種子法とは?
種子法は専門的な法律なので、ご存じない方の方が多いと思います。
私も昨年の廃止時にネットで話題になるまで知りませんでした。
種子法とは正式な名前を『主要農作物種子法』と言って、昭和27年(1952年)に制定された法律です。
『主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他助成の措置を行うことを目的とする。』
と定められています(衆議院HPより)。
稲、麦、大豆など、戦後の食糧増産という国家的要請を背景に、国・都道府県が主導して、優良な種子の生産・普及を進める必要があるとの観点から制定されました。
種子法が制定されたのは、第2次大戦終結のためのサンフランシスコ講和条約が発効された翌月というタイミングで、戦中から戦後にかけて食糧難の時代を経験した日本が、「食料を確保するためには種子が大事」と、主権を取り戻すのとほぼ同時に取り組んだのがこの種子法の制定だったようです。
種には『固定種』と『F1種』の2種類がある

野菜などを選ぶときに栽培方法は吟味しますが、その種子がどうなっているかまで考えたことはあまりありませんでした。
私は子供の頃から様々な植物を育てることが好きで、食べた後のビワの種を植えたり、朝顔から種を取って翌年に植えたりなどして、常に何かしらの植物を育てていました。
しかし、10年ほど前から種が発芽しにくくなったことに気が付きました。
その時は自分の植え方に問題があるのだろうとしか考えませんでしたが、どうやら流通している植物の種が変化していたようでした。
固定種とは?
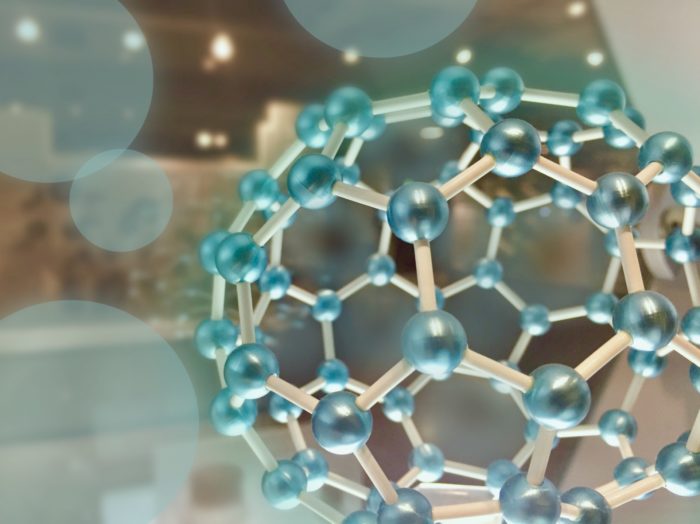
まず固定種についてご説明します。
できた作物から種を「自家採種」し、少しずつ時間をかけて品種改良を行ったもので、地域の土地に適した形質を、年月をかけて固定化したものが固定種です。
形質が固定されている為、できた種を翌年に蒔けばまた同じ形質をもった野菜が収穫できます。
この種からできた作物には生命の多様性があり、形や大きさが不揃いなことがあったり、また収穫時期にバラつきが出たりしますが、その野菜が持つ本来の味を味わえると言われています。
また、環境への適応力も高いと言われています。
F1種とは?
次にF1種です。
Filial 1 hybridの略で、一代雑種やハイブリッド種とも呼ばれます。
異なる性質を持つ親同士を組み合わせると、第1世代は必ず同じ形質を持つというメンデルの法則を利用したもので、収穫時期や形、大きさなどを揃えることができます。
ただし第2世代(F2種)になると、形質にバラつきが出てきます。
そのため、F1種からは次世代の種を採取しません。
それなら種ができないようにしてしまおうと、F1種の作物が交配しないようにしようするために使われているのが、雄性不稔の遺伝子を使う方法です。
本来であれば雄性不稔の株は遺伝子異常なので自然淘汰されるのですが、その遺伝子を利用して交配しないようにしています。
この遺伝子異常の作物を食べることがどの程度人体に影響があるのかは、まだはっきりしていません。
これらのことを踏まえて、次の記事では、種子法の問題点を具体的に考えてみたいと思います。






